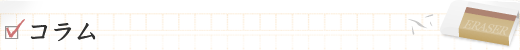- TOP
- > コラム
国から地方への税源移譲はどうあるべきかを分析・提言
こんにち、地方分権は、世界的な奔流になっています。それは分権化によって、公正かつ効率的な行財政が可能となるからだといわれています。
日本では、1995年に地方分権推進法が制定され、その成果は、2000年の地方分権一括法の施行に結実しました。これを分権改革の第1段階というならば、2002年から取り組まれた「三位一体改革」と呼ばれる財政の分権化は、地方分権改革の弟2段階といえるものですが、結局税源移譲が過小なため地方行財政の運営を困難にしてきました。現在は、税源移譲の過小が認識され府県市町村あわせて4〜5兆円規模の第2次税源移譲の必要性とあわせて道州制の導入が検討される、第3段階に入ったといわれています。
本書『分権的地方財源システム』で著者は、この第2次税源移譲の規模やオプションを提示しています。
第2次税源移譲論では、目下、所得税単独移譲論と所得税・消費税併用移譲論が激しく対立し論争されています。
著者の基本的スタンスは、後で述べる「協調・連帯学派」の立場で著者独自のシミュレーション分析をすることにより、所得税単独移譲(つまり個人住民税単独拡充)が優位であることを明らかにしています。すなわち、所得税の基礎税率10%部分を府県に5%、市町村に5%移譲し、個人住民税を拡充するとともに、軽度の累進税率を堅持すべき、というものです。これは、所得税の5%部分が地方移譲され、個人住民税が比例税化(府県民税4%、市町村民税6%)した現在では、さらに5%部分の地方移譲と軽度の累進税率の復帰を主張することになります。
ところで、地方分権改革が21世紀の奔流になっているとはいえ、分権改革論のすべてが同一方向で主張されているわけではありません。その考え方には、大きく分けて2つの立場があります。
まずは、市場原理を過度に重視する新自由主義と親和性をもった小泉構造改革を評価する「効率重視学派」があります。効率重視学派は、競争的分権論の立場から財政効率化の最も有効な手段として地方分権を位置づけます。そこでは住民選好の結果「低福祉サービス・低負担」が選択されても分権の目的は達成されるのです。これに対し、「協力・連帯学派」は、協調的分権論の立場から、地方自治の充実(つまり地方政府や住民の自治能力の涵養)の実現を第一義におき、効率化はこの目的を補完する手段として位置づけます。著者は、後者の「協力・連帯学派」の立場から、大きな政府の非効率や官僚主義を批判しつつも資本主義経済の世界的危機のなかで政府の積極的役割(規制・介入)は不可欠であると主張します。
本書は、地方分権改革の本来の意義・方向性とはなにかを問い直すなかで、地方分権を実質化する国から地方への税源移譲のあり方を分析し提言しています。財政の研究者やエコノミストだけでなく行政・自治体関係者が共通に抱えている地方財政問題を考えるうえで有益な示唆を得ることができる一冊です。


<前のコラム | 次のコラム> | バックナンバー