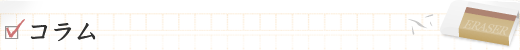- TOP
- > コラム
「政権交代」を超えて
―2009年夏 誰もが熱くなる衆院選
いま、夢中になっているテレビドラマがある。「官僚たちの夏」(毎日放送)だ。ミスター通産省こと風越や「所得倍増計画」をうちあげた池内首相はじめ、登場人物は立場や思想・イデオロギーを超えていずれも気骨があって、人間像がクリアなのがいい。
しかし、それ以上に私の関心をひくのは、昭和30年代(1955〜65年)の政治家や官僚の情熱である。敗戦からようやく立ち上がり、これからの日本をどんな国にするのか、国民をどうのようにして幸せにするのか―貿易自由化か、それとも国内産業の保護か―熱い思いに支えられたそれぞれの政策をめぐる男たちの闘いは、観ている者までをも熱くさせる。
「官僚たちの夏」から約50年後の2009年8月。衆議院選挙の火ぶたが切られた。マスコミや市民の関心は、継続の自民党か変化の民主党か、ともっぱら政権交代に集中している。また、今回の選挙は「マニフェスト(政権公約)選挙」ともいわれている。が、停滞する経済、行き詰る社会福祉、少子高齢化で先行きがみえにくい現実がごろごろ転がっているにもかかわらず、それとも、そんな社会だからこそであろうか、選挙の争点はみえにくい。
ただ、はっきりしているのは21世紀初頭の今は、これまでのような「利益の政治」を標榜する時代ではなく、市民も「痛み」や負担増といったマイナス面を自覚せざるをえない時代だということだろう。
シリーズ「先進社会」(法律文化社刊)や『ローカル・イニシアティブ』(中公新書)などで、日本の政治を鋭く分析し、そのゆくえを指し示してきた藪野祐三教授(九州大学。政治学)は、小泉政権以降の日本政治を分析するにあたり、そして、今回の選挙をみるのに興味深い指摘をしている。
「政権交代」をキーワードとした枠組みだけで政治をみるのではなく、「利益の政治」から「負担の政治」へと政治そのものの枠組みの変化に注目することが必要だという。しかも、「負担の政治」の時代だからこそ、コスト意識をベースにして市民は自らの生活を描くことができるのだ。そして、藪野教授は市民に問う。『負担の政治』に耐えることができるか、と(9月刊『失われた政治』)。
そういう意味で、今回の衆院選は市民の政治意識・感覚、さらに市民としての責任が問われる選挙といえよう。もはや政権交代だけでは日本は変わらない。政治家や官僚だけが熱くなっても変わらないのだ。マニフェストの評価・採点だけでなく、それを点検し、実現していくのも市民一人ひとりに委ねられている。
今回の選挙で私たちは、政治への期待が薄らいだ「失われた政治」の向こうに、どんな生活空間を築くことができるだろう。


<前のコラム | 次のコラム> | バックナンバー