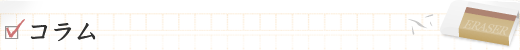- TOP
- > コラム
裁判員制度における「裁判官」の役割
8月3日、初の裁判員裁判が東京地裁で開かれ、6日までの4日間の連続開廷で結審しました。20歳以上の一般国民が裁判員として刑事裁判に参加する裁判員制度。その第1号事件は、テレビや新聞で大きくとりあげられ、制度に対する国民の関心の高さをうかがわせました。多くのニュースでは、事件だけでなく、裁判員の質問回数・質問内容から、座った場所、その表情などまで、こと細かに報道。そして、裁判員裁判は一般に、“出だしは好調”として評価されているようです。
ただ、実況中継さながらの詳細にすぎる報道のあり方には違和感も覚えます。そもそも、それだけ詳細な報道がなされていたのに、裁判官から裁判員に対して、「刑事裁判の原則に関する説示」が、いつ、どのように行われたのかについては、詳しく触れられていません。否認事件ではなく、量刑が焦点となったせいかもしれませんが、否認事件でなくとも、説示はなされたはずです。「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則など、刑事手続の基本が裁判員にきちんと伝えられたかどうかは、裁判員の判断ひいては評議の内容を左右しかねません。従来の裁判に引き続き、裁判官の果たす役割は大きいといわざるをえないでしょう。
近年明るみにでた冤罪事件でも、捜査機関の問題が強調されますが、木谷明先生は、新著『刑事事実認定の理想と現実』のなかで、元裁判官の立場から“仮に違法捜査が行われていたとしても、裁判官が、公判廷での被告人の弁解を真摯にうけとめ、それを見抜いていれば、冤罪は防げたのではないか”と、本来裁判官が果たすべき役割の重要性を説いています。
「刑事裁判の理想=無辜の不罰」とする著者は、裁判員制度に代表される今回の司法改革では、密室取調べによる虚偽自白の問題や、証拠開示制度の不備による被告人に有利な証拠の排除といった問題を克服できておらず、冤罪防止の観点からみれば欠陥の残るものだと主張します。だからこそ、まず裁判官が、その制度上の欠陥を理解し、それをカバーするためにも、先入観や思い込みを捨て、被告人ひとりひとりに対して真摯に耳を傾けるべきだ、とも。
長年にわたる経験から「慣れ」によって判決を下してしまいがちな職業裁判官に、「裁判慣れ」していない裁判員の視点が加わることで、適正な事実認定が実現できるのではないか、また、それによって裁判官の意識が変わっていくのではないか、と期待する声もあります。ただ、制度が新しくなり裁判員が参加するだけで、刑事裁判がよくなるわけではありません。弁護人、検察・警察、そして裁判官それぞれが、不完全な制度であることを踏まえたうえで、改善してゆく姿勢を持つことが何より重要でしょう。もちろん、裁判員となる私たち市民も同じです。


<前のコラム | 次のコラム> | バックナンバー