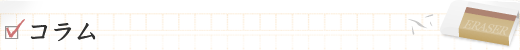- TOP
- > コラム
裁判員制度と日本人の法意識
今年5月に裁判員制度が導入されてからすでに4か月が経ちました。
評価はさまざまですが、一般には国民が司法に直接参加する制度の定着に向け、まずまずの滑り出しとみられているようです。
国民が裁判員として司法にかかわることで、裁判官の専門的判断に頼ってきた従来の司法を変える契機となりうるかもしれませんが、裁判員が被害者遺族の感情等を考慮して、裁判が厳罰化に傾く弊害も懸念されています。実際、全国初の裁判員裁判となった東京足立区の隣人殺害事件では、被害者遺族が懲役最低20年を求めたのをふまえて、従来の判例よりも重い懲役15年の判決が言い渡されました。
司法手続における国民の参加や国民世論の影響の是非を議論することはもちろん大切ですが、そもそも日本人は、法や裁判というものにどうかかわってきたのでしょうか。
10月刊行の『史料で読む日本法史』では、日本人が歴史的に培ってきた法や裁判に対するイメージについて、興味深いテーマを選んで解説しています。
明治期の近代法の導入に先立ち、裁判以外の紛争解決手続が発達していたことが紹介されます。たとえば中世には、年貢の奉納をめぐって「和与(わよ)」という和解手続がしばしば利用されていました。江戸時代には、村落共同体間の紛争が「内済(ないさい)」という調停手続により処理されました。こうした紛争解決手続の対象事項は、主には土地や金銭をめぐる民事事件でしたが、刑事事件に関しても客観的な法の適用以外の要素が考慮されました。たとえば戦国時代には、藩の秩序を守るため理由の如何を問わず、紛争を起こした当事者双方に同一の処罰を科す「喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)」という法が存在しました。江戸時代には、島流しの刑を受けた幼年者を一定の年齢までは親類に預けおくよう命じるなど、紛争の実際的な解決が図られたのです。
日本では、血縁や領域の支配等をめぐる社会的、集団的関係のなかで権利が具体的に主張されました。西欧のように客観的、体系的規則に基づく裁判よりもむしろ、紛争当事者間の話し合いや譲歩を図りながら衡平な社会関係を維持するかたちで法の運用がなされていました。良いか悪いかは別に、日本人がどのような法意識を培ってきたのか、また裁判を含む司法手続をどうとらえてきたのかを問うことは、国民がその一翼を担う裁判員制度の運用・改善を図るうえで有益です。
裁判員になりうる学生や市民には、紛争の実情に即して法律の妥当な解釈を行う能力が求められます。六法などの、いわゆる実定法科目を重視する法学部やロースクールでは、日本法史などの基礎法科目はカリキュラム上あまり重きを置かれていませんが、さまざまな制度改革がなされている今こそ法史学の視点が必要なのかもしれません。
実定法の解釈を学ぶ学生だけでなく、日本史を学びなおそうとする社会人にも、本書は日本法への新たな関心をもたらしてくれるでしょう。


<前のコラム | 次のコラム> | バックナンバー